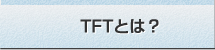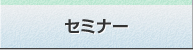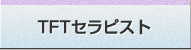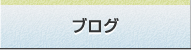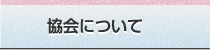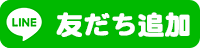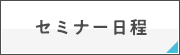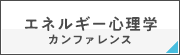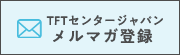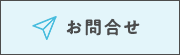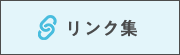お知らせ
Information
お知らせ
Information
エネルギー心理学カンファレンス2017/7/22-23
2017年7月22-23日(土日) 会場:東京未来大学
日程
エネルギー心理学カンファレンス2017(1日目)
 |
7/22(土)13:00〜17:00 タッチフォーヘルス・ワークショップ「キネシロオジーの基礎と家庭の医学」 講師:小堀 健太郎(カイロプラクター/タッチフォーヘルスインストラクター) |
エネルギー心理学カンファレンス2017(2日目)
TFT事例発表申し込み(6/10まで)
 |
7/23 (日)9:20〜11:00, 14:45〜17:00 TFT災害支援報告・体験会・事例紹介・エネルギー心理学・ 講師:森川 綾女(心理士/TFTトレーナー) 日本TFT協会理事長、国連世界人道促進機構・NOHE人権大使(健康&医療支援) |
 |
7/23 (日)13:00〜14:30 講師:藤本 昌樹(大学准教授/臨床心理士/TFTトレーナー) 東京未来大学准教授、シーディング・リソース代表、 |
抄録
■ 7/22(土)13:00〜17:00
タッチフォーヘルス・ワークショップ「キネシロオジーの基礎と家庭の医学」
Touch For Health Workshop
小堀 健太郎 Kentaro Kobori(カイロプラクター/タッチフォーヘルスインストラクター)
TFT原因診断テクニックの基礎であるアプライドキネシオロジー(AK)は臨床家のテクニックで、そこからジョン・シー博士は「タッチフォーヘルス」という家庭のための施術を目指しました。
そして、さらに心理的な要素と身体の重要な関連性に気づき、ヴァージニア・サティアとの交流から、ブリーフセラピーの要素が加わり「自分の健康、そして人生」を他人任せにするのではなく自分で管理し責任を持って充実した人生を送ることを目的としたセラピーに発展しました。
本講座は、専門家向けの講座として、キネシオロジーの背景や基礎を学び、心と体、エネルギーとの関係を筋テストやツボを通して体験します。
タッチフォーヘルスキネシオロジーって何?
1970年代にアメリカで生まれたタッチフォーヘルス(TFH)ですが、創始者のジョン・シーD.C. (ドクター・オブ・カイロプラクティック)がカイロプラクティックへ通っている患者さん自身の為に自宅でも簡単に出来るセルフケアを伝えたところから始まり、医師や薬にだけ頼るのではなく、自分の健康や人生に責任を持つ「自己責任モデル」が世界中に急速に広まっていきました。
専門的な知識がなくても家庭でお互いを助け合う為に安全に使う事ができ自然治癒力を高める事ができる効果的なツールという事から「家庭用医学の決定版」とも言われています。
TFHの背景には、アプライド・キネシオロジー(A.K.)があり、西洋医学と東洋医学そして心理学や栄養学を融合させ、統合的にセラピーを行うことが出来るという事からプロのカイロプラクターはもとより、スポーツトレーナー、理学療法士、整形外科医、内科医、歯科医、看護師、自然療法家など多くの専門分野に取り入れられ活用されてきました。
TFHを標準的な医療と合わせて使う事により薬や手術の必要性を減少させ医療効果を上げ回復期間の短縮に役立つ役割を果たしてきました。
特徴
A.K.は医師が患者に行う「治療モデル」であるのに対してTFHは一般向けの健康法として「自己責任モデル」「教育モデル」と言われています。
TFHは「A.K.の概念と伝統的中医学、セルフケアと自己啓発の考えに基づきシンプルで安全な健康法」と位置付けられています。
特にA.K.に含まれていなかった「目標設定(健康と人生に対する)」と「五行メタファー(気づきの言葉と質問)」は創始者Dr.シーが重要視した大きな特徴と言えます。
明日からすぐ使えるテクニックのご紹介!(デモンストレーションと体験)
- 目標設定とメタファー
- どんな症状にも使える背骨の調整法:脊椎反射ポイント
- 簡単な筋肉のコリの解消法:筋紡錘テクニック
- セルフケアにも使える内臓ケア:神経血管ポイント
- 筋反射テストの方法①
- セルフケアにも使える感情ストレスの解放:ストレスチェックとESR(感情解放)
- 心因性の痛みの見極め方と調整法:筋反射テストとESR(感情解放)
- エネルギー調整:8の字エネルギー
- 筋反射テストの方法②(消化に関する筋肉)
- 栄養テスト:筋反射テストと筋肉を強くする食べ物、必要なものを選ぶ食べ物テスト
- セルフケア:水、スイッチング、視覚の調整、聴覚の調整、クロスクロール、経絡マッサージなど
参考文献
- 「タッチforヘルス健康法」 ジョン・シー 市民出版社
- タッチフォーヘルスハンドブック「五行メタファー」 ジョン・シー マシュー・シー 市民出版社
- 「完全版タッチフォーヘルス」 著:ジョン・シー マシュー・シー 日本キネシオロジー総合学院
- 「アプライド・キネシオロジー入門」 著:Robert Frost 監訳:栗原修 医道の日本社
■ 7/23(日)9:20〜11:00, 14:45〜17:00
「TFT・エネルギー心理学・HRV(心拍変動)最前線」
The Cutting Edge of TFT, Energy Psychology, Heart Rate Variability
森川綾女 Ayame Morikawa, M.D., Ph.D., M.B.A.
(一般社団法人日本TFT協会理事長・TFTセンタージャパン/心理士)
昨年に続いて、エネルギー心理学の最新情報を報告する。
1970年代終わりのキャラハンの思考場という概念から始まり、感情や思考を含む、人のエネルギーに働きかける新しい心理学の分野として発展し、米国心理学会にも認められた。そして、TFTは米国政府機関である「物質乱用とメンタルヘルスサービス組織SAMHSA(Substance Abuse and Mental Health Service Administration)」にエビデンスある治療法として登録された。
特に次のことに有効である。
「個人のレジリエンス・自己概念、自律、トラウマ・ストレス関連の障害と症状、抑うつとうつ症状、一般的な機能と健康、恐怖症、パニック、全般性不安障害とその症状、特定不能およびその他のメンタルヘルスの障害と症状ラウマやうつ、パニック」。
日本では専門家を中心に広がり、大規模災害で実際に用いられ、その効果は臨床で認められ、今では精神医療や心理臨床など広い分野で用いられる技法となっている。熊本地震からの復興を1年にわたり支援してきた活動を災害支援モデルとし、「60分で一生分の治療」ができると言われるほど非常に早く処理できるブリーフセラピーとしてのモデルを報告する。その他の臨床事例を交えながら、藤本先生の愛着への治療アプローチ、会場での体験会とともにTFTの多彩な効果と実践を体験していただく。
TFTをまだ学んだことのない方にもぜひ参加していただきたい。
同じエネルギー医学・心理学の分野でHRV(心拍変動)の研究もされてきた。
キャラハン博士は早くから健康の客観的な指標であるHRVに注目して研究してきた。
健康や自律神経の機能を評価するのに使われるHRVであるが、近年、HRVを呼吸法によって改善し、レジリエンスを高める方法がプログラム化され、ADHDに有効なプログラムとしてエビデンス登録されている。
スポット的に瞬時に症状を改善するTFTのタイプとは異なり、生理学的なレベルでのベースラインを改善していくHRV呼吸法は、組み合わせも非常に相性が良く、どちらもレジリエンスのセルフトレーニングになることから、クライエントの自律訓練や自己コントロールに非常に有効である。
スマートフォンやパソコンで簡単に自己モニターできるようになったバイオフィードバックの分野は、トレーナーとなっていつでもガイドしてくれる上に、心理状態やエネルギーを可視化できるようさらに技術が進んでいくであろう。
今年、日本でスタートしたハートマス研究所のHRV呼吸法の講座のイントロダクションとしたい。
※HRVバイオフィードバックをお持ちの方は、ご持参ください。
参考文献
- つぼトントン【6月出版予定】 森川 綾女 (著)
- TFT思考場療法臨床ケースブック―心理療法への統合的応用
スザンヌ・M. コノリー (著), Suzanne M. Connolly (原著), 森川 綾女 (翻訳) - TFT(思考場)療法入門―タッピングで不安、うつ、恐怖症を取り除く ロジャー・J. キャラハン (著), 穂積 由利子 (翻訳)
■ 7/23(日)13:00〜14:30
「愛着理論の基礎とトラウマ臨床への応用」
The Basics of Attachment Theory and the Applications to Trauma Treatment Practice
藤本 昌樹, Ph.D., L.C.S.W., P.S.W.(東京未来大学准教授)
愛着理論は、Bowlbyによって提唱され、動物行動学の知見や精神分析学的な理論を土台とし、Ainsworthらの研究などによって検証、実証されてきた理論である。Bowlbyの愛着理論に関しての著作は、「母子関係の理論」として邦訳され、広く知られている。
このように、乳幼児時期の母子関係を出発点とした愛着の理論の研究は幅が広く、社会心理学的な分野から始まった、成人期における対人関係の作業モデルとしての愛着としての研究や、恋愛におけるパートナーの選択、AAI(成人愛着面接)の手法を使用した愛着の世代間伝達など多岐に及ぶ。そして、近年、愛着理論は、発達性トラウマ、複雑性トラウマの治療、解離などを理解する上で大きな中心的役割を担ってきている。
しかし、日本においては、2〜30年前では、愛着といえば発達心理学領域に属するもので、臨床心理学と関連するものだとは十分に理解されていなかった。それゆえに、以前に大学の心理学の授業で愛着を学んだものにとっても、愛着と臨床との関連について十分に理解できていないのが現状ではないだろうか?
そこで今回は、Bowlbyの愛着理論の基礎、それによって得られた知見を確認し、新しい視点として「情動制御」という観点からみた場合、愛着がどのように理解されうるか等について、限られた時間において手短に解説していきたい。
そして、愛着の本質的な理解と、実際に臨床的にどのような意義を持つのかについても、基本的理解のレベルから、トラウマ臨床との関連が深い愛着の本質的な意義に触れ、なるべく、わかりやすく臨床的な意義についても論じていく。
心理臨床の中で、トラウマよりむしろ愛着の問題の方が大きいと感じ、スザンヌ・コノリーが見つけたTFTの愛着パターンも合わせて紹介したい。
参考文献
-
「子どものこころの発達を支えるもの: アタッチメントと神経科学、そして精神分析の出会うところ」
グレイアム ミュージック (著), Graham Music (原著), 鵜飼 奈津子 (翻訳) -
「アタッチメントと臨床領域」 数井 みゆき (著), 遠藤 利彦 (著)
-
「愛着理論と精神分析」 ピーター フォナギー (著), Peter Fonagy (原著), 遠藤 利彦 (翻訳), 北山 修 (翻訳)
参加費
| 参加日程 | TFT協会員 | 会員以外 |
| 2日間(全日) | 10,000円 | 12,000円 |
| 7/22のみ | 5,500円 | 6,500円 |
| 7/23のみ | 6,500円 | 7,500円 |
申し込み
1例あたり15分(質疑応答含む)の発表です。
会場
東京未来大学・大講義室
<最寄り駅まで>
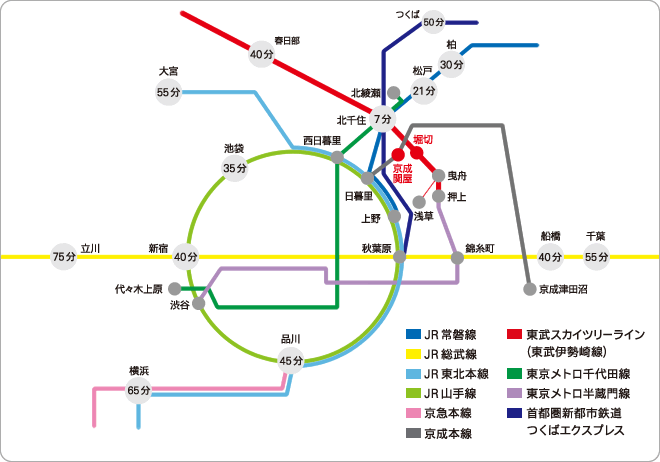
<周辺地図>
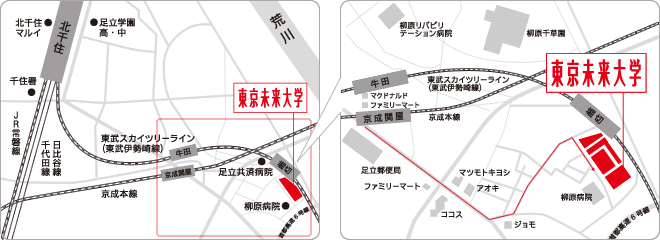
東京未来大学大学HPアクセス:http://www.tokyomirai.ac.jp/info/access.html